「ゲーム慣れし過ぎたオトナの固定観念が最大の壁」――『カービィのエアライド』をデザインした主:桜井政博の言葉に触れて役立つと感じた人生論をプレゼン。
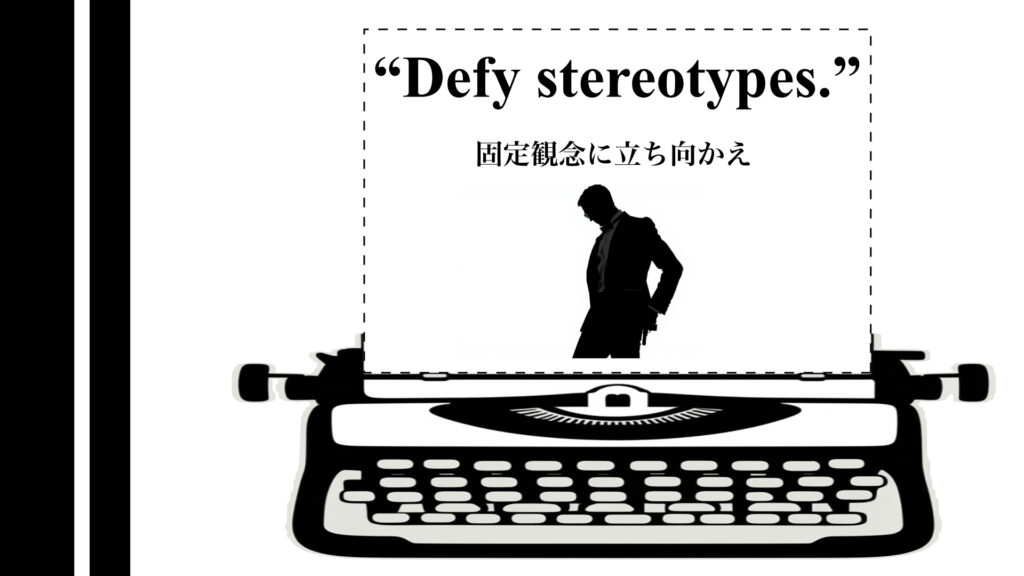
おはようございます。「フィルム&プレゼンテーション」へようこそ!フリープレゼンターの🦉あーさんと申します。
この記事の性質はコラム寄りですかねぇ。一応記事カテゴリーは「プレゼンTips」としているのでプレゼンノウハウに関する内容ではあります。が、比較的カロリー控えめな記事なのでサクッと読んでそんなこと考える人もいるのか程度に聞き流して良いとも思う。
が!
桜井政博のゲームについて思うこと Think about the Video gamesについてどん中身なのか、うっすらわかるので桜井政博という偉人?に興味ある方の参考材料になるかも。
inputして“おっ⁉️”と感じたことについてゆるーーーく綴っていくとしましょう。everydayプレゼンしている変人にしかできないアウトプットがたぶんある。なお今回はNOエミュレート。すっぴんでお届けします。
桜井政博の言葉
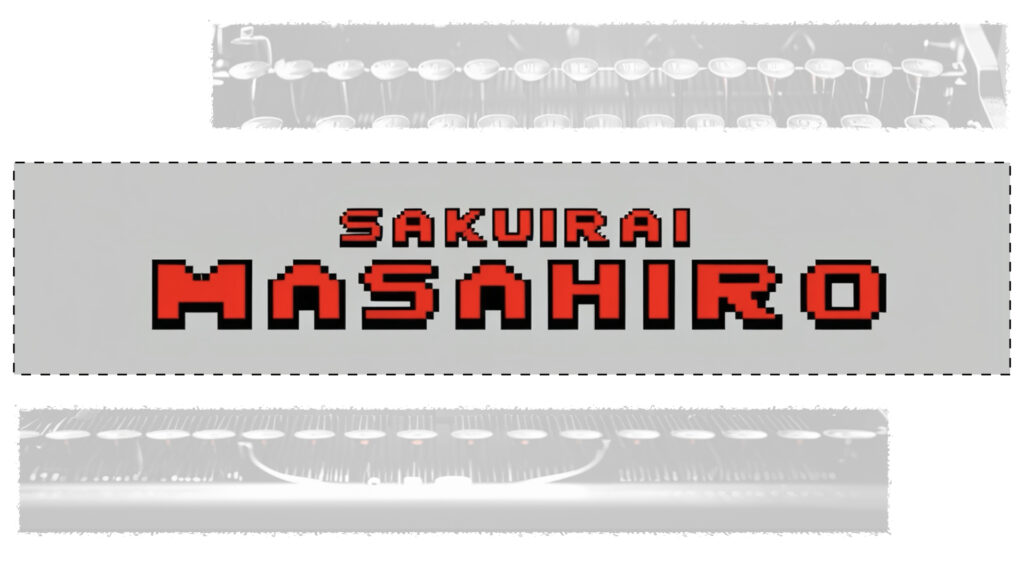
書籍「桜井政博のゲーム作るには」に掲載されているコラムVol.13・14「カービィーのエアライド」を読みました。そこには興味深い一文が登場したので紹介します。
「ゲーム慣れし過ぎたオトナの固定観念が最大の壁」
ゲームソフト『カービィのエアライド』をデザインした主の設計思想が如実に現れた短文。
これはゲームに限らずあらゆる物事に言えることだなぁ~~~と痛感した次第。人というのは歴史の上に立っている。自らの人生で摂取してきた情報が偏見となることも知らずにそれを常識だと思い込む。思い込んでしまうといった方が正しいでしょうね。
アインシュタインの偏見への解釈
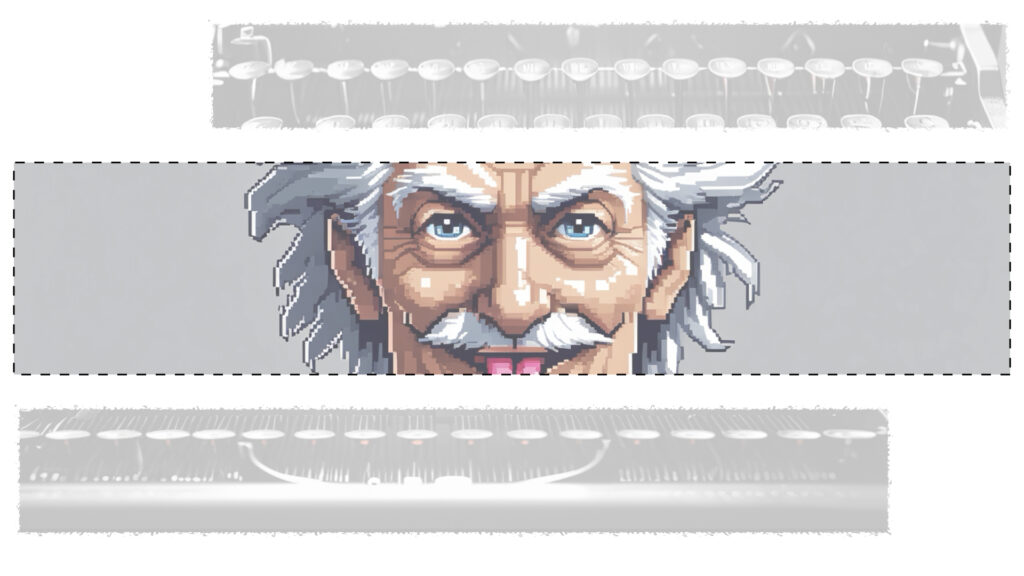
「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションである(または「偏見のコレクションでしかない」)」
アルベルト・アインシュタイン が残したとされるこの言葉が示す通り、人は最初期の刷り込みで自ら意図せずして色眼鏡をかけてしまう生き物。
色眼鏡をかけている自覚を持てと言われても無理な話で、そう易々と自らの価値観を覆せるものではない。
ではどうすれば良いのか……。
固定観念に立ち向かうにはどうすれば良いのか
その答えは誰一人として模範解答を持っていないというのが事実なのでしょうが、ある程度参考にできるメンターがいることも確か!
そのメンターとは再び登場、桜井政博氏❗️
『カービィーのエアライド』のゲームデザインにそのヒントがあると私は考えます。
馴染み深いコンテンツと新機軸をセットで相手に届ける
「エアライド」「ウエライド」「シティトライアル」。シティトライアルを除く2つのメインモードは比較的一般に馴染み深いレースに近しいそれ。この二つがあることで作品の核である自由度青天井の「シティトライアル」という新たなる遊びへの抵抗感を抑制しつつレースゲームとして同作をリリースできたのではないかというのが私の推測。
この推測が合っているかはともかく、抱き合わせ作戦というのは非常に有効であることはイメージしやすいのではないでしょうか?
ピーマンの肉詰め。栄養豊富でも子供には苦すぎるピーマンもお肉と1セットにすれば食べてくれる確率上昇―――これに通じる考え方ですね。
プレゼンにしろコミュニケーションしろ、メッセージを咀嚼してもらうには相手と接点を深めるしかない。大衆受けする“何か”を武器として持っているだけでその成功確率は自ずと上昇することでしょう
結びに

如何だったでしょうか?
今回は「ゲーム慣れし過ぎたオトナの固定観念が最大の壁」―――という桜井政博さんがコラムに記したユニークなメッセージにスポットライトを浴びせ、筆者の見解を述べさせていただきました。
私の見解がタメになるかは定かですが桜井さんのコラムが栄養豊富かつ面白いことは保証します。是非お手元に揃えて自らの血肉としてみてはどうでしょう?

カービィのエアライドの思い出
最後に少しスペースを設けて小学生時代の私の思い出を一つプレゼンします。レースゲームをプレイした経験もあるのだけど下手くそで全然楽しめなかった私でしたが、エアライドは違った。レースゲームのセンスがなくとも楽しめる柔軟性、パーティー性、中毒性―――何もかもが素晴らしいゲーム体験でした。
自分でゲームソフトを持っていたわけではなかったので友人宅にお邪魔した時に必ずプレイしていましたね。う~~~~ん良い思い出だ!
そのゲームが22年の時を経て続編が出ようとは思わなんだ。是非、Nintendo Switch2ユーザーは新作に手を出して欲しいと心より思います。
筆者はまずSwitch2をゲットするところから始めます。抽選に2度落ちたので3度目の正直というやつが発動するはずだ!
このブログではプレゼンノウハウの提供・実践や競走馬・ウマ娘シリーズの魅力の紹介をあの手この手を駆使して自由に🪽フリーダムに行なっております。
毎日読んでくれる方・ブックマークしてくれる方・SNSで拡散してくださる読者の方々。誠にありがとうございます。そして、ここまで読んでいただき重ね重ね感謝。多謝です。
またのご縁をお待ちしております。
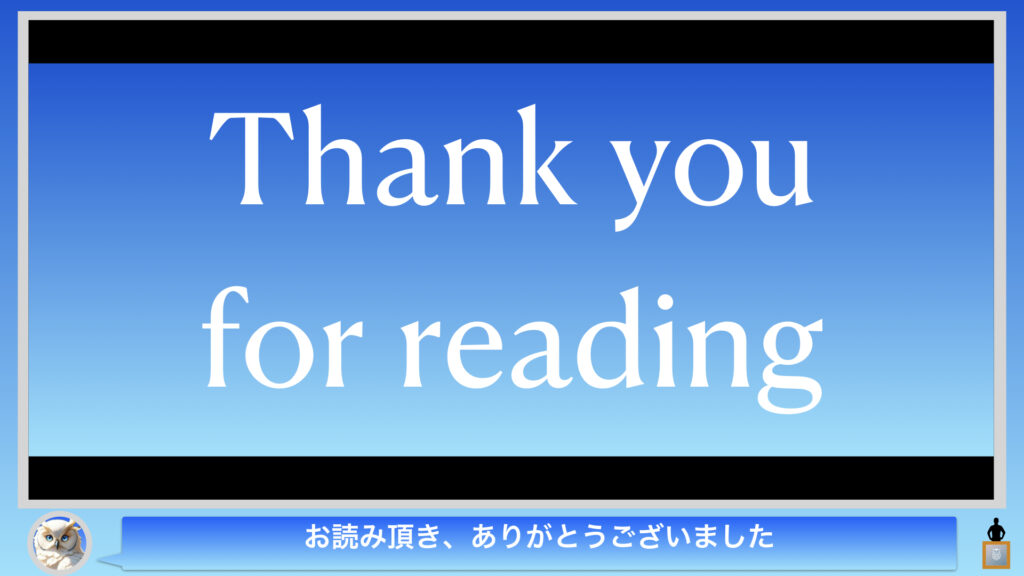
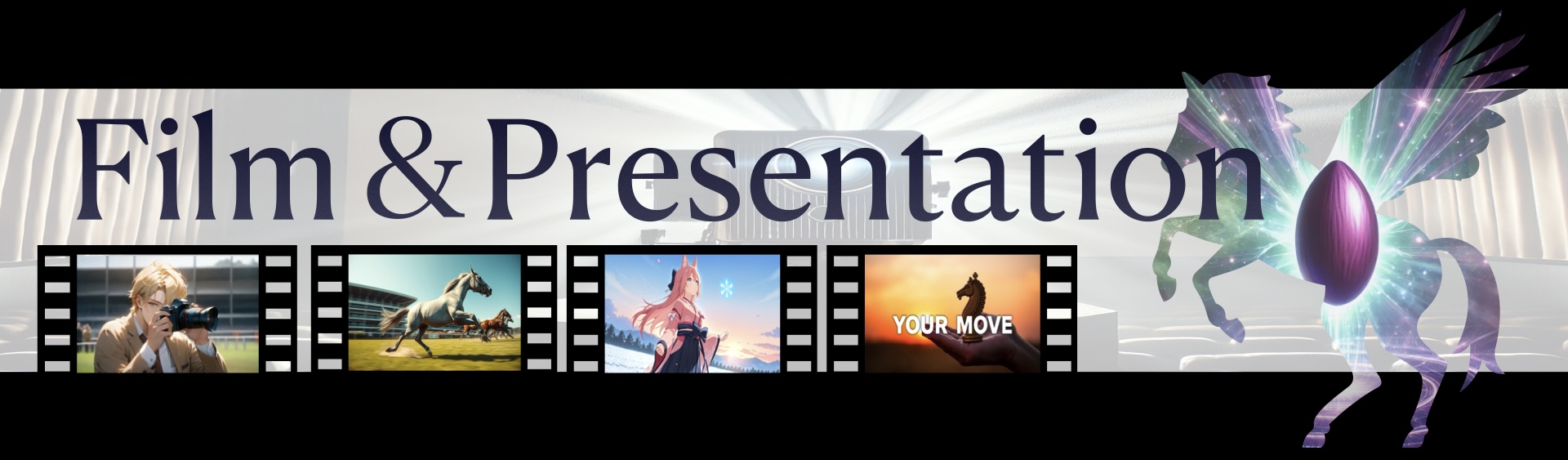


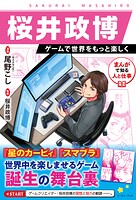


コメント